老後の持ち家はどうする?
家の維持or住み替えの判断ポイントを解説
老後の持ち家はどうする?
家の維持or住み替えの判断ポイントを解説
老後の住まいの現状は持ち家派が多数!
 実際に、老後はどのような住まいを選ぶ人が多いのでしょうか。
実際に、老後はどのような住まいを選ぶ人が多いのでしょうか。
統計データを元に、高齢者の住まいの現状を見ていきましょう。
高齢夫婦は9割近くが持ち家に住んでいる
総務省の「住宅・土地統計調査」によると、高齢者(65歳以上※)がいる世帯の多くは持ち家に住んでいます。
※世界保健機関(WHO)の定義に基づく年齢です
| 持ち家 | 賃貸 | |
|---|---|---|
| 高齢者のいる世帯 | 82.1% | 17.8% |
| うち、高齢者のいる夫婦のみの世帯 | 87.4% | 12.5% |
| うち、高齢者の単身世帯 | 66.2% | 33.5% |
出典:総務省「平成30年 住宅・土地統計調査」から当社作成
実は持ち家と賃貸の割合は20年前からほとんど変わっていません。「将来は賃貸より持ち家派」のほうが多数という現状は同じです。
一方で、高齢者の単身世帯の持ち家率は約66%と、複数の家族で過ごす世帯と比べると賃貸の割合がやや多めです。近年は複数人の単身高齢者が共同生活を送れるシニア向けシェアハウスが登場するなど、老後の住まいの選択肢は広がりつつあります。今後は単身世帯を中心に、持ち家と賃貸の割合に変化が見られるかもしれません。
「狭くても利便性があり、資金的に余裕を持てる住まい」が理想
不動産流通経営協会の「シニアの住宅に関する実態調査」によると、45歳以上の人は老後の住まいに対して以下のポイントを重視しています。
- 金銭面の負担が軽く、手元にお金を残せること
- コンパクトサイズであること
- 生活利便性の高い場所であること
上記の意識はエリアにかかわらず全国共通で、年齢を重ねるほど意識が強くなっていきます。65歳以上になると、上記に加えて「バリアフリー対応など設備の充実度」を重視する傾向強くなります。
また、実際に老後の住み替えを考えている、または経験している人は全体で5割を超えており、年齢別の傾向は以下のとおりです。
- 45~54歳・・・約4割
- 65歳以上・・・約6割
50歳前後では住み替えを考えていなかった人でも、実際に年を重ねていくと必要に迫られるケースもあり、住み替えを考えるようになるのではないでしょうか。また、住み替えの意向や経験がある人の住み替え先は大半が持ち家です。ここでも「住み替え後も持ち家派が多数」という現状が浮き彫りになっています。
出典:一般社団法人 不動産流通経営協会「シニアの住宅に関する実態調査」
老後の住まいは現状維持?住み替え?判断ポイント
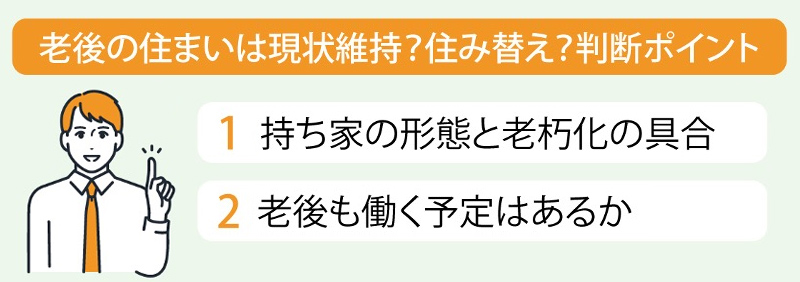
先の調査結果をふまえて、ここでは「持ち家に住み続けるのか、それとも住み替えをするのか」を判断する際のポイントを解説します。
1.持ち家の形態と老朽化の具合
持ち家が戸建て
老朽化によって設備や間取りが不便になっても、戸建てであればリフォームや建て替えで利便性の高い住まいに変更できます。
とはいえ、戸建てが郊外にあり駅や街中から離れている場合は、ライフスタイルに合わなくなってくる可能性もあるでしょう。リフォームや建て替えで今後の暮らしを充実したものにできるのか、老後の生活をイメージしながらじっくり考えていきましょう。
持ち家がマンション
マンションは利便性の高い立地にあることが多いですが、築年数が経過すると区分所有特有のトラブルが起きやすくなります。
たとえば、大規模修繕の際に管理組合で話がまとまらない、修繕するための資金不足が発生しているなどです。
万が一、大規模修繕の資金が不足していると、大規模修繕自体ができなくなったり、不足している金額分をマンションの戸数で割った金額を一括で徴収されたりする可能性があります。
そのため、築20年を経過しているマンションにお住まいの方は、今後の大規模修繕計画の状況を確認してみるといいでしょう。
2.老後も働く予定はあるか
老後も働く場合、定期的な収入があることでローンも賃貸契約も結びやすく、住まいの選択肢はぐっと広がります。
ただし、独立して自営業やフリーランスとして働く場合と、現役時代の会社で継続して雇用されて働く場合とでは、各種契約の組みやすさは大きく異なります。
特に住宅ローンは金融機関によって利用条件が異なるため、現役の今から身近な金融機関に条件等を相談しておくのがおすすめです。
一方、老後に働く予定がなく、年金収入のみで暮らす場合は、賃貸契約をはじめ各種契約が組みにくくなります。まとまった資金があればローン無しでリフォームや住み替えを検討できますが、ここで資金を使い過ぎないように注意しましょう。
働かない場合は、「できる限り資金を使い過ぎない住まい」を選ぶことが基準になるでしょう。
老後の住まいの方向性がある程度決まったら次は何をする?
 老後の住まいを現状維持するのか住み替えるのかがある程度決まったら、次はどのような行動を起こせばいいのでしょうか。
老後の住まいを現状維持するのか住み替えるのかがある程度決まったら、次はどのような行動を起こせばいいのでしょうか。
ここでは持ち家に住み続ける場合と住み替える場合にわけて紹介します。
持ち家に住み続ける場合
将来も持ち家に住み続ける場合は、老後の住まいを意識したリフォームを検討してみましょう。
戸建てであれば、お部屋につまずきやすい段差があったり階段の段差が急だったりする場所では家庭内の事故を招いてしまうおそれがあります。
自宅での転倒事故を防ぐために、床の段差をなくす工事をする、階段に手すりをつけるといったリフォームが考えられます。
また、築年数が古い家は建築基準法による耐震基準が改正前に建てられたケースもあるでしょう。建築確認申請の日付が1950年~1981年6月1日以前に建てられた家は、旧耐震の基準で作られているため、震度5以上の地震が来た場合、倒壊するおそれがあります。
とはいえ、工法やメンテナンス状況によっても異なります。ホームインスペクション(住宅診断)をおこない自宅が安全がどうかを確認し、状況によっては耐震リフォームを検討してみてもいいかもしれません。
住み替える場合
住み替える場合は、まず賃貸へ住み替えるのか、別の分譲住宅へ住み替えるのかを検討しましょう。
【賃貸住宅に住み替える】
賃貸を考えているならば、年金とは別に安定した収入があるほうが安心です。収入が年金のみの場合は賃貸契約の審査に通りにくくなってしまうので注意しましょう。
また、通常の賃貸のほか、サービス付き高齢者住宅(サ高住)という方法もあります。自由度が高い暮らしである一方、安否確認や生活相談のサービスを受けられるので一人暮らしの人にもおすすめです。入居費や月額利用料、サービス内容は施設によって異なるので入居前に複数の施設を見てみるといいでしょう。
ほかにも介護が必要な状況であれば、介護型の老人ホームやケアハウスも選択肢に入ってきます。
どのような生活を望むのか、どのような環境が必要なのかを考えて住み替え先を検討しましょう。
【分譲住宅に住み替える】
分譲住宅へ住み替える場合は、まず自己資金はどのくらいあるのかを洗い出しましょう。自宅を売却後に住み替え先の物件を一括購入できるのか、一括購入が難しそうであれば住宅ローンは借りられそうかなどを考える必要があります。
また、自宅を売った資金をまるまる使ってしまっては老後の生活に不安も残ってしまいます。住み替え時には資金計画をしっかりと立てることが大切です。
金融機関で相談も可能ですので、不安なことがあれば窓口で相談してみるといいでしょう。
まとめ

将来の住まいにはさまざまな選択肢がありますが、現在、多くの高齢世帯は「老後も持ち家」に住んでいます。単身世帯については賃貸派が3割いるものの、実際には持ち家に住んでいる人が多数という現状は20年前から変わりません。
老後も今の持ち家を維持する、あるいは今の持ち家から住み替える場合に大切なポイントは、当事者(夫婦)だけではなく家を受け継ぐ人への影響を考えることです。
たとえ思い出がつまった大切な持ち家でも、不便な郊外にある家は相続しても売却できず、空き家になってしまうリスクがあります。空き家になれば老朽化が進み不法投棄や犯罪等のリスクが高まるため、管理する人の負担が重くなってしまう可能性があります。
老後の住まいは自分たちだけで決めるのではなく、住まいを受け継ぐ人とも一緒に相談して決めるとスムーズかもしれません。
また、持ち家を維持するかどうかは、家の状態や今後の働き方なども判断ポイントになります。本記事を参考に、ご自身の住まいはどうするのが理想的なのかをぜひ考えてみてくださいね。
※この記事は2024年1月現在の情報を基に作成しています。今後変更されることもありますので、ご留意ください。
 老後の住まいの現状は持ち家派が多数!
老後の住まいの現状は持ち家派が多数!
 高齢夫婦は9割近くが持ち家に住んでいる
高齢夫婦は9割近くが持ち家に住んでいる
将来は現在のお家に住み続ける? それとも住み替えする?
家族構成の変化や年齢を重ねると共に住まいに求める条件が変わってくることもあります。
本コラムでは持ち家を維持するかどうかの判断ポイントについて紹介しています。まだまだ先のことと思わず、将来の住まいについて一度考えてみるのもよいかもしれませんね★
コラム監修 北國銀行 竹内 愛